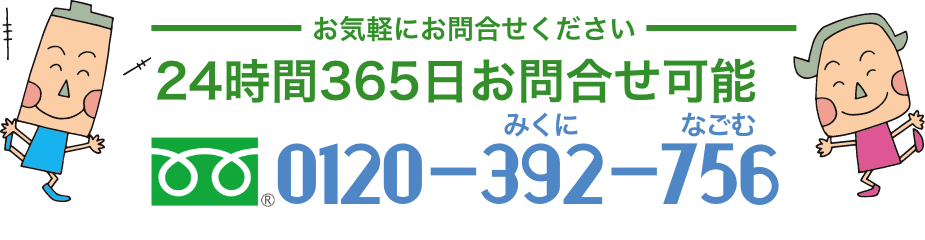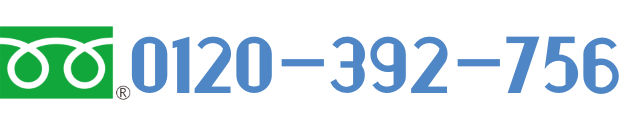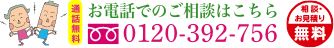親の終活準備は、いざという時に子どもの負担の軽減にもつながります。
面と向かっては言いにくいけれど、自分の親には終活を進めてもらいたい、というのが本音でしょう。
普段、避けていた話題かもしれませんが、コロナウイルス感染症の影響でなかなか帰省できないからこそ、
会える機会に、あるいは電話などでじっくり話し合ってみませんか。
1. 親の終活は子どものためになる
あなたの親に次のようなことがあったとき、すぐに対応することや回答することはできますか?
終活の準備をして、エンディングノートに記載するなどしておけば、
子どもの負担は大きく減ることになりますし、親の希望も確認することができます。
「終活」とは何か、という点については、下記をご確認ください。
終活とは何をするのか 人生の後半期をよりよく生きるための計画作り
1-1. 突然倒れて、入院・手術することになったとき
高齢になれば、病気やケガのリスクは高まります。
そのとき病院ではこのようなことを聞かれます。
「持病やアレルギーはありますか?」
「これまで手術したことはありますか?」
「今、どんな薬を飲んでいますか?」
親の病歴を知っていますか? 昔、病気したことは何となく覚えていても、
正確にはわからない人がほとんどでしょう。
しかし、入院時には必ず聞かれる情報です。
親が入院・手術となる前に情報をつかんでおけば治療にも役立つはずです。
もちろん、現在の体調についても確認しておきましょう。
1-2. 認知症の症状がでたとき
認知症の見守りは24時間休む間もないので、他人にケア(介護・見守り)をお願いすることが増えていきます。
認知症の介護のプロは、次のようなことがわかると、いい介護ができると言います。
「好きな食べ物」
「好きな音楽」
「どんな人生を歩んできたか」
認知症だからといって、何もかもわからなくなるわけではありません。
その人の好きなものを知り、過ごしてきた人生を理解して寄り添うと、本人も安心しますね。
介護にはお金がかかるので、年金や資産の大まかな情報も把握しておきたいものです。
1-3. 亡くなったあとのこと ~お葬式・お墓~
親が亡くなったあとの最初の関門は「お葬式」です。悲しみにひたる間もなく、
葬式の準備を進めなければなりません。そのときに葬儀業者には次のようなことを伝える必要があります。
「葬式には何人くらい来るか」
「菩提寺(お墓のある寺)はどこか」
「家の家紋は何か」
「写真(遺影)はどれを使うか」「祭壇はどのランクにするか」
規模によっては百万円以上のお金が動くイベントの内容を、1~2日で決めなくてはなりません。
葬式に来てもらいたい人やどんな葬式にしたいかなど、判断するための情報が残されていれば、
余裕をもって準備できます。
1-4. 死後の手続き・相続
人が亡くなると多くの手続きが必要です。
どんな暮らし方をしていたか、どのような契約があるか、
一から調べなければならないとしたら、手続きの負担は非常に大きくなります。
中でも、多くの人が大変だと口をそろえるのが遺品整理・処分です。
親が一人暮らしの場合には、衣服や書籍、ノートなどの身の回りの持ち物のほか、
家具や家電など、ほとんどのものが不用品になります。
思い出の品々もあれば、押し入れや物入れに詰められた頂き物の数々など、
数十年の積み重ねは大量の荷物となっているはずです。
不用品はあらかじめ処分しておくこと、「価値があるもの、誰かに残したいもの」を
ノートなどに書いておくこと、が行われていると、荷物処分も大変楽になると思います。
そして、相続は亡くなった人の財産の承継です。
事前の準備がなければ、せっかく築いた財産をうまく引き継ぐことができないかもしれず、
相続人同士の無用な争いを招くかもしれません。
1-5. 人間関係・親戚付き合いなど
親族とのつながりが希薄になりつつあると言われてはいるものの、お祝い事や葬式・法要でのお金のやり取りでは、
お返しなど、親の付き合いを継承しなければならないこともあります。
また、生前にお世話になった方がわかれば、亡くなったことを連絡したり、離れて暮らしている間の生活の様子などを聞いたりすることができます。
2. 親子で一緒にしておきたい終活とは
終活のスタートとして、気軽に始めていただきたいのは「1.エンディングノートを書いてもらう」ことです。
その上で、「2.具体的なアクションを起こしてもらう(対策を行う)」ようにします。
高齢になると書くことが面倒になることもあるので、直接会ったり、話したりできるのであれば、
ゆっくりおしゃべりしながら、聞き書きしてあげてもいいかもしれません。
2-1. エンディングノートを書いてもらう
親の万一に備えて、次のようなことを聞いておきましょう。
①~⑤に備えるには、どういう情報が必要かを、矢印で表示しています。
近年、高齢の親との関係でトラブルの多い「介護・認知症」と「相続」については、
しっかり話し合っておくことをお勧めします。

2-2. 具体的なアクションを起こしてもらう(対策を行う)
エンディングノートを活用して情報を集めることがまず重要です。
その上で、具体的な対策を始めてもらうといいでしょう。
片付けなどは、思い出話を聞きながら、少しずつ一緒に進めてあげられるといいですね。
①身じまいについて
数十年かけて増えてしまった荷物等の片づけや処分を、高齢の親が行うのは大変です。親の意思を確かめたり、
思い出話を聞いたりしながら、親が納得するかたちで進められるようにサポートしてください。
このほか、使っていない預金口座を解約しておいたり、ネット関係を含めた契約を整理したりしておくといいでしょう。
②サポート体制を整える
遠方に住む親に何かあってもすぐに駆け付けることはできません。
身近に見守り、支えてくれる人がいないようであれば、地元の地域包括支援センターや親の友人・知人と連絡を取って、いざというとき対応してくれる体制を作っておきましょう。
その人たちには、自分の連絡先を伝えておくことも忘れずに。
③認知症に備えた財産管理
認知症になると、その人の財産管理(預貯金等の口座からの引き出し、不動産の管理・処分)ができなくなって困ることがあります。
介護のお金が足りない、家の修繕ができない、アパートなどの管理ができないということも起こりえます。
お金や不動産の管理が難しくなった時に備えて、「金融機関に代理人届けを出しておく」
「親子で任意後見契約を結んでおく」などの対策ができれば安心です。
④相続対策
金融資産や不動産の処分や組み換え、遺言を作成するなどの対策は、元気なうちに行っておくことが望まれます。
入院したり介護施設に入ったりすると、本人が動けなくなるだけでなく、感染症対策のため親子であっても簡単には会うことができなくなるからです。
3. 一緒に終活をするうえで気を付けるべきことは
親に終活の提案をする上で気を付けたいのは、感情的な問題です。
遺言などの死を連想させる対策は、嫌がる方が多いので、無理に強要して感情の行き違いを起こさないようにしてください。
終活は、その人のこれまでの人生の集大成で、亡くなった後のことだけでなく、残りの人生を悔いなく生きるための活動でもあります。
苦労したことも楽しかったことも親の人生です。親の話や想いをよく聞いてあげて共感し感謝を伝えながら、
明るい雰囲気で進めることが大切です。
一緒に親を見守り、見送ることになる、きょうだいとの関係にも気を付けましょう。
きょうだいでも価値観や考え方は異なりますし、それぞれの生活もあります。
誤解を招いてトラブルになることを避けるためにも、できるだけきょうだい間で話し合った上で進め、
情報は共有しておきましょう。
私がNPO法人ら・し・さで、オリジナルのエンディングノート(ら・し・さノート®)を作成し、普及活動を始めた頃、
まずは自分からということで、当時70歳代後半の母の財産整理を始めました。
父はすでに亡く、母は実家で一人ぐらしをしています。最初はイヤそうな態度だったので、
何回か通っておしゃべりしながら少しずつ年金や預貯金、証券会社等の情報を聞き出して一覧表を作り、
書類をファイルにまとめてあげたところ、「あーこれで安心して暮らせる。長生きしても大丈夫ね。ありがとう。」
と大喜び。母も不安に感じていたのですね。
それ以来、怪しい電話や郵便、訪問があると、すべて相談してくれるようになりました。
思い出話や愚痴などを聞きながらの作業だったため、母の人生をよく理解できるようになったことも収穫のひとつです。兄や妹にも大まかな情報は伝えていますので、私たちきょうだいも安心です。
現在93歳の母は、いつ亡くなったり、認知症になったりしてもおかしくない年齢ですが、
おかげさまで楽しく元気に暮らしているようです。新型コロナウイルス感染症が蔓延しているため、
毎年恒例の旅行や親族の集まりが自粛中なのは残念ですが、最後まで楽しく過ごしてもらえたらと思っています。
(記事は2020年8月1日現在の情報に基づきます)

 資料請求
資料請求
 お見積もり無料
お見積もり無料