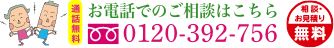厚労省は2022年人口動態統計月報年計(概数)を発表した。死亡数は156万8961人で、前年の143万 9856人より12万9105人増加した。今後も高齢化は進み、2040年には死者の数が167万人でピークを迎えると推計されている(※1)。「多死社会」に突入すると、様々な課題が予想されているが、その一つが『在宅死』の増加だ。遠くない現実に、家族はどう備えておけばいいのか。
超高齢化社会→多死社会へ 在宅死が増加するという現実に家族は
現在、自宅での看取りは全体の約17%ほどでしかない。7割以上の人が病院や診療所で死亡していて(※2)在宅死を他人事と感じられる方も多いかもしれない。
しかし、2035年には団塊世代が85歳以上になり(※1)、その先には死亡者が大きく増える『多死社会』が待っている。一方で、政府は入院ベッドを減らし、在宅医療や介護の拡充を目指している。つまり、今後は在宅死の割合が増加することが必至なのだ。それは家族にとってなにを意味するのだろうか。
神奈川県に住む山本さん(仮名)は、胃がんの夫を看病し、最後の18日間は自宅で共に過ごした。山本さんにとっては、在宅死という選択は、振り返ると“理想の最期”につながっていたという。
「最後の日は、ソルベっていうフルーツのアイスを夫と半分ずつ食べました。メールを打っていて、横にいる夫を見たら動かなくって、ふざけちゃだめよ、死んだ真似なんてしないでっていったくらいです」
山本さんの夫は、山本さんの横で、眠るように息を引き取っていたという。経験したことのない自宅での看取りに戸惑いもあったが、夫の最期は安らかにみえた。

山本さんの在宅医療を担当したのは、神奈川県逗子市『さくら在宅クリニック』の内田賢一医師だった。在宅医として、年間に約120人の自宅での看取りに寄り添っている。山本さんの夫の最期は、本人にとってだけでなく、家族にとっても幸運だったと内田医師は話す。
「患者さんは痛みに関してはほとんどコントロールされていました。家族の看病も数週間でした。ただ、あの時間が数か月続いていたら、山本さんは参っていたと思います」
どのような最期を迎えるかを、医師も、家族も、本人も、“完璧に演出”することはできない。しかし、在宅医療が広がる中で、理想に近づくための大きなカギを握ることになるのは家族であると内田医師はいう。
「在宅死は、もちろん亡くなる患者さんの一人称の問題でもあるんですが、一番の決定権は、家族です。家族がギブアップするかしないか、患者さんの望みを家族が許容できるかどうかなんです。
多くの人は、人の死をほとんど見たことがない、未経験なんですね。経験があったとしても、70年代以降、病院で亡くなる人がほとんどで、病院任せでした。
在宅死では、想定していないことが突然降って湧いてくることになります。自分の近くで家族が亡くなるリアルに、思い違いのようなことがあるなら、少しずつ考えを切り替えておくことで、下準備ができるのではないかと思います」
在宅死に向き合う家族に、在宅医が伝えたい3つのこと

『さくら在宅クリニック』内田賢一院長 年間約120人の看取りに寄り添う
内田医師は、在宅死を経験した家族たちに寄り添ってきた経験から、大きく3つのことを知っておいてほしいと話す。一つ目は、過度な不安は必要ないということだ。
①難しいことではない②病院でなくても③家族でもできるんですよ
ということです。
皆さん、自宅で看ることに不安や心配が多いようです。『私にできるんでしょうか?』『痛くないようにできますか?』『苦しくなくできますか?』と家族からは本当にいろんな質問をうけます。
そもそも、医学的に介入の余地がもうない場合は、病院にいる理由はないです。痛みを取る、苦痛を取ることに関しては、家でも、病院でも、やることは一緒で、医療者に任せればいいのです。そうした部分で、難しいことを家族に要求することはないです」
経験したことがないものに対する漠然とした不安はいらない、ということのようだ。しかし、だからといって簡単なことだというわけではもちろんない。在宅医療には、家族に身体的、そして心理的な負担が生じるということも、知っておいてほしいことの一つだという。
「患者さんは、終末期の不安もありますし、だんだんいろんな訴えが強くなっていきます。それに対しては、家族が、医療者と同じように応えなくてはいけません。
もうちょっとずらしてくれとか、ちょっと起こしてくれとか…病院だったら医療者がやっている仕事を、家族がやらなくてはいけません。しかも24時間、夜勤状態が続くという部分は身体的に難しいところです。
さらに、心理面では、僕らは仕事として対応できる部分があるのですが、家族にとっては、目の前で家族が亡くなっていくというのは非常に酷で、大きく感情の部分で対応するので、気持ちの振れ幅がとても大きいです」
身体的、心理的負担が掛け算で家族にのしかかる…時にSOSも大切
未経験のことをするだけでも大変なのに、24時間の向き合いが、何週間、何か月と続きかねない在宅医療。しかも、身体的、心理的、という二つの負担は、足し算でなく、掛け算で家族にのしかかるものなのだという。
だからこそ、内田医師は必ず家族に伝えていることがあるという。それは、どんなに自宅で看取るつもりでいたとしても、時にSOSを出すことも選択肢として持っていてほしいということだ。
「絶対に家で看なくてはいけない、というわけではないということです。
人間は感情の生き物で、身体がつらくなってくると、例えば、亡くなっていく患者さんと喧嘩になってしまう場合もあるんです。『なんでそんなわがままをいうんだ』などと言ってしまって、その後に家族は後悔する。でも、繰り返してしまう。そして『もう限界です』とお話になることは、よくあることなんです。
もしどうしても駄目だったら、ホスピス、緩和ケア病棟、もしくは療養型病院などもあります。一つ逃げ場所を作りながら看ることもできます。これは必ずお話している心構えです」

現状では病院死が大多数だ。そのため、家族の死との向き合い方にある程度の距離をおくこともできたといえるだろう。一方で、厚労省の調査(※3)では、自宅で最期を迎えたいと希望している人は約7割にのぼっている。
家族が在宅死について正しい知識と心構えをもつことは、多死社会だからというだけでなく、本人の希望に沿った人生のフィナーレに家族としてどうかかわるかを考えることにもつながっているのかもしれない。
※1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 人口動向基づき将来投影した場合(令和5年推計)
※2 厚生労働省「人口動態統計」(22年)
※3 厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」(平成30年3月)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/558296?display=1
より転用させて頂きました。

 資料請求
資料請求
 お見積もり無料
お見積もり無料